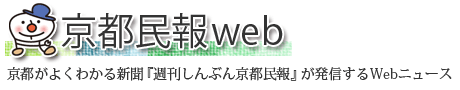京都市・巨大給食センターの問題点 日本共産党京都市議団・玉本なるみ議員、江本佳世子議員に聞く/48校2万2千食調理・配送 9月議会に契約議案

京都市の全員制中学校給食を巨大給食センター方式で実施する計画を巡り、市は開会中の9月議会に整備運営事業を担う特別目的会社との契約のための議案を提出しています。議決されれば、今月には事業契約を締結する予定です。一方で、日本共産党市議団の調査や議会論戦で問題点が次々浮き彫りになり、巨大給食センター計画の無謀さが明らかとなっています。この間の論戦などで何が明らかになったのか、玉本なるみ、江本佳世子両議員に聞きました。
「民間まかせ」食の安全確保に不安
──市は契約議案を提出しましたが、現時点でどんな問題点が明らかになっていますか
玉本 市は2万2000食を調理し、48校に配送するセンターについて、民間資金を活用し公共事業を行うPFI手法のうち、BTO方式(*)で行う方針です。入札により7月、東洋食品(東京都)を代表とするグループ会社が落札。同グループ会社が特別目的会社「みやこの学校給食サービス」を設立し、この会社と市が約436億円で契約する議案となっています。
巨大センターの問題とともに、整備運営をPFI手法で民間任せにしていいのかが問われています。
担い手が民間となれば、利益を生む必要があります。今回の契約で言えば、利益は東京本社に吸い上げられる一方、人件費を抑えるために働き手は非正規が基本となり、給食の安全性は低下する可能性は大きくなります。
また企業が破綻・撤退した場合、給食が提供されないことになり、そのリスクは致命的なものになりかねません。
落札の内容も問題です。7月の文教はぐくみ委員会で共産党の冨樫豊議員が追及しましたが、落札の際の審査結果は非常に低いものでした。総合点は1000点中789・5点。そのうち性能点は700点中489・5点です。内訳を見ると、食育支援は30点中18点にすぎません。これだけ低い評価で、給食の安全を守り、食育を支援することができるのでしょうか。
入札参加1社のみ「無謀な計画の表れ」
しかも、入札に参加したのは東洋食品グループ1社だけで、他の1社は途中で辞退してしまいました。もともと市がPFI手法に基づき、実施方針などを公表し、事業者から意見を募集した際には、業者からの質問は14社、340件に上っていました。しかし、入札参加が1社だけになったというのは、巨大センター計画がいかに無謀で破綻しているか、その表れだと思います。
他市の巨大センターでは■2時間喫食「守れない」常態化/虫・毛髪・木片…異物混入相次ぐ
──共産党は、2時間喫食や食の安全、食育の問題など繰り返し追及してきました
江本 学校給食衛生管理基準では「調理後2時間以内に喫食することが望ましい」と規定しています。巨大センターでこの基準が守れるのか、食中毒のリスクはどうなのか、共産党は他都市の実態調査をし、繰り返し市教委を追及してきました。
府内の木津川市には2センターがあり、一つは6200食を提供する府内最大の学校給食センターとなっています。両センターとも3年連続、「2時間喫食」が守れず、保健所から指導を受けており、共産党が木津川市議会で追及しています。
政令市の状況を見ると、A市の一番大きいセンターは23校9108食を調理・配送し、ある中学校では調理から給食準備開始までに3時間34分かかっていました。22校1万5000食を調理・配送するB市センターでは、最長で3時間42分かかっていました。
こうした事実を示し、昨年11月議会の代表質問で2時間喫食が守れるのかとただしました。これまで、市教委は2時間喫食を「マスト(必須)」と答弁してきましたが、「努める」と答弁を後退させています。
玉本 さらにこの間、堺市では6月から二つのセンターで計43校、2万4000食を提供していますが、異物混入が65件(虫、毛髪、木片など)発生。神戸市は今年1月から第1センターで9000食を20校に提供し、ここでも異物混入が154件起こっています。大規模調理では、衛生管理がおざなりになっていることが明らかとなっています。
栄養教諭の配置も問題です。文科省の基準に基づくと京都市のセンターではわずか3人の配置です。市教委は7月の文教はぐくみ委員会で、二つの調理ラインをつくる一棟2場方式で整備するので、倍の6人の配置を求めていきたいと答弁しました。
議会論戦と合わせ、運動も力を発揮しています。「京都市によりよい中学校給食をめざす署名推進実行委員会」が学校調理での実施を求め、粘り強く署名運動を展開してきました。当初センターで対象となる全校分を調理・配送する計画を発表しましたが、大きな批判の下、センターは48校分として、残り13校分は二つの民間調理場が担う計画に変更するなど、大規模センターの矛盾が次々と露呈しています。
南区南西部に広域避難場所〝空白地域〟が
──センター予定地の問題もあります
江本 南区の建設予定地の塔南高校グラウンド跡地は、もともと東吉祥院公園で、広域避難場所にもなっています。市は既に公園の廃止処分を行い、センター建設が始まれば、広域避難場所の指定取り消しを行うとしています。
ところが、取り消しとなれば、南区南西部の広域避難場所は桂川を越えた久世橋西詰公園1カ所のみとなります(地図参照)。9月8日の総務消防委員会では、他都市(東京都、横浜市)では避難距離基準を持っていることを示し、広範囲に広域避難場所の空白地域が生じてもいいのかとただしました。
建設予定地は浸水想定区域
また、センター予定地は浸水想定区域です。福知山市のセンターでは、2014年の豪雨災害で配送車がすべて水没して給食が止まり、復旧まで約2カ月かかりました。浸水想定区域に給食センターを新設しようとする今回の計画は災害リスクが反映されているとは言えません。
現在、住民の方々は違法な公園廃止処分の取り消しを求めて、提訴しています。
──巨大センターをやめさせることはできるでしょうか
玉本 問題は山積し、強引に進めれば進めるほど計画は行き詰まっていくでしょう。大規模センターの流れは国主導により全国で進められてはいますが、政令市では、さいたま市が自校方式、札幌、大阪、北九州3市は学校調理方式で実施しています。
「署名推進実行委員会」から発展した「京都市によりよい中学校給食をめざす連絡会」と「南区塔南高校跡地の今後と給食センター問題を考える会」の二つの住民運動を軸に、議会と市民が今まで以上に力を合わせれば、大きな力を発揮するでしょう。私たちも頑張ります。
*BTO方式 民間事業者が資金を調達して公共施設を建設(Build)。施設完成後にその所有権を国や地方公共団体に移転(Transfer)した上で、施設の維持管理・運営(Operate)を行う、PFIの事業形態です。