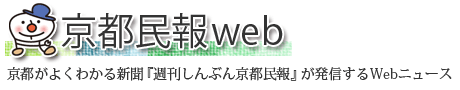「ふたたび被爆者をつくらないために」 戦争被害「受忍論」と国家補償求める被爆者の闘い/京都大学人文研教授・直野章子氏が講演

京都弁護士会「憲法改正問題全国アクションプログラム」
日本政府は、「戦争の被害は国民が等しく受忍しなければならない」(受忍論)という主張を盾に、広島、長崎への原爆投下を含む空襲の民間人被害者に一切の謝罪と補償をしていません。この「受忍論」について考える講演会が6日、京都市内で開催されました。
京都弁護士会主催の「憲法改正問題に取り組む全国アクションプログラム」。母と祖父母が広島で被爆した、歴史社会学者の直野章子・京都大学人文科学研究所教授が「戦争被害を受忍しない」と題して講演しました。
報復や核武装ではなく核廃絶へ
直野氏は、昨年、ノーベル平和賞を受賞した日本被団協に代表される「被爆者」が反核平和の象徴となったのは「必然ではない」と指摘。米国に対する報復や核武装を求めるのではなく、「身をもって体験した〝地獄〟の苦しみを、二度とだれにも味あわせたくない」(1984年発表の被団協基本要求)と核兵器廃絶運動に至った背景には、原水爆禁止運動の誕生と被爆者自身の闘いがあったと述べました。特に、1955年に初開催された原水禁世界大会で、被爆者が全国からの参加者と直接交流することで、これまで語れなかった苦しみを共有でき、勇気づけられたことが、自らの組織化=日本被団協の結成(1956年8月)につながったと解説しました。
日本被団協が核兵器廃絶とともに掲げた要求が原爆被害者への国家補償であり、ノーベル平和賞授賞式のスピーチで田中熙巳(てるみ)代表委員が「原爆で亡くなった死者に対する償いは、日本政府はまったくしていない」と訴えたことは、被爆者の積年の思いを代弁したものだったと強調。日本政府は、戦後、軍人・軍属らには恩給など総額約60兆円の補償を行う一方で、民間人の被害には受忍論を盾に補償を拒否。被爆者に対しては、放射線被害を「特別の犠牲」と位置付けて、被爆者の援護に関する法律で手当ての対象としただけだと述べ、「戦後80年を経過して、『援護』と名の付く法律はあっても、国家補償として規定された原爆被害者援護法すらないのが現状。被団協は一貫して受忍論に反対してきた」と話しました。
今を生きる私たちを「被爆者」にしないために
直野氏は、被団協が基本要求の中で援護法など国家補償について、「同じ被害を起こさせないための第一歩」「核戦争被害を『受忍』させない制度を築き、国民の『核戦争を拒否する権利』をうち立てるもの」と説明していることを紹介し、「今を生きる私たちを『被爆者』にしないための要求でもある」と述べ、「『ふたたび被爆者をつくらない』ことを自らの使命として闘ってきた歴史の積み重ねがあったからこそのノーベル平和賞だった」と訴えました。
ノーベル平和賞授賞式ツアーに参加した、被爆者の花垣ルミさんが自身の被爆体験とともに、ノルウェー・オスロで市民や国会議員と交流したことなどを報告しました。