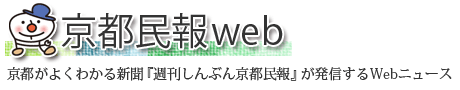公費1兆円投入で「高すぎる国保」大幅引き下げを 〈宝の議席必ず 倉林明子参院議員の実績〉“救えるはずの命が救えない”日本ではいけない

「未就学児均等割半額に」廃止へ一歩前進
政治家志した原点 京都市議時代から一貫して論戦
高すぎる国民健康保険料(税)が払えず無保険となり、医療機関にかかれず命を落とす人がいる現状に、「『救えるはずの命が救えない』という日本でいいはずがない」、と国保制度の課題を取り上げてきた倉林明子参院議員。看護師だった1990年代、保険料が払えず手遅れで亡くなる人が京都市で相次いだことが政治家を志した原点です。国保の課題解決を京都市議時代からのライフワークに、均等割・平等割の廃止、保険料の引き下げを一貫して国に求めてきました。
0歳児にも賦課まるで「人頭税」
参院議員2期目、保険料の負担軽減で前進したひとつが、均等割保険料の未就学児分については5割を公費負担にしたことです(2022年4月施行)。倉林議員は、国保にのみ均等割保険料があり、負担能力に関係なくゼロ歳児にもかかることから、古代の「人頭税」みたいなものだと批判。子どもが多い世帯ほど保険料負担は増え、「子育て支援の逆行にほかならない」と繰り返し均等割の廃止を求めてきました。
それまで「子どもも含めて応分の負担をしてもらう仕組みだ」と開き直っていた政府を動かし、ようやく被保険者の5割減額に踏み切りましたが、倉林議員は、「均等割を就学前までなくすことに思い切って踏み込むべき」(21年5月27日、厚労委)と迫りました。
コロナ禍減収3割減で減免
コロナ禍の下で、収入が減った加入者から「保険料が払えない」という声が相次ぎ、国も前年度比3割以上の減収が見込まれる世帯への減免制度を創設しました(20年4月)。このコロナ特例国保減免は、民商も活用を呼びかけ、加入者に喜ばれた制度で、倉林議員が国会質問(同年6月、参院厚労委)で引き出した大臣答弁が力になりました。
倉林議員は、申請書類や申請方法の簡素化を認める厚労省の事務連絡の周知徹底を要請したなかで、事業収入等が3割以上減少するとみなして減免し、結果として3割以上の減収にならなかった場合の国の対応について確認。「国の財政支援の対象になる」(加藤勝信厚労相=当時=)との答弁を引き出し、申請運動に一役買いました。
倉林議員は、国民健康保険の加入者の構成が、前期高齢者の比率が高い上、無職、非正規労働者など低所得者も増えている一方で、保険料が高すぎるという構造問題を指摘。中小企業従業員が加入する「協会けんぽ」と比べて2倍も高い保険料の実態を示して、公費負担増額を求めてきました。
政府が18年度に国民健康保険の「都道府県化」を強行し、それまでは個々の市町村が運営していた国保を都道府県との共同運営に変更したことが国保料(税)の値上げに拍車をかけました。
さらに、75歳以上の医療保険料や国保料の引き上げにつながる健康保険法等改定(23年5月)が強行されました。この動きに、国の責任を後退させ、国民に負担増を迫るものと反対し、同法案の撤回を求めました。
法案審議で倉林氏は、過酷な国保料負担の実態を京都市在住のシングルマザーの世帯を例に紹介。納期中1回(全10回)の国保料の4300円は米10㌔(当時)、約1カ月分に当たり、夏はクーラーも使わず、トイレは1日1回しか流さないという生活実態だとし、財政安定化基金も活用して「緊急に国保料の引き下げを」と主張。反対討論では、国保料統一の強行により、自治体が独自に行っている負担軽減策をやめれば、国保料が高騰し、国保加入者に過酷な負担を強いると指摘し、国庫負担の抜本的増額と富裕層、大企業にこそ応分の負担を求めることで財源を確保すべきと訴えました。
高すぎる故に医療から排除
全日本民医連は毎年、経済的事由により受診が遅れて死亡に至った事例調査を実施し、高すぎる保険料が「受診抑制」を招いていることを明らかにしてきました。倉林議員は、この結果から、「高すぎて払えない国保料が無保険を生んでいる」と保険料を引き下げるために公費負担を大幅に増額するよう繰り返し要求してきました。
また、保険証は持っていても、窓口負担を心配して、医療機関へのアクセスが遅れることも指摘し、一部負担金の減額や支払いを免除する制度(国保法44条)の徹底が必要だと指摘。「医療を受ける権利が排除されるようなことがあってはならない」と強調し、一部負担金減免が使えるよう、制度の周知と国の財政措置の大幅な増額を求めました(24年4月、参院厚労委)。

医療受ける権利守る論戦に期待
左京社会保障推進協議会事務局 前野 弘さん
左京区では、コロナ禍の2020年から、食料の無料提供と暮らしの相談に応じる「左京連帯ひろば」を同実行委員会やボランティアスタッフ、社保協で取り組み、1~2カ月に1回くらいの頻度で続けています。
コロナ禍以降も物価高騰が続くなかで「連帯ひろば」には毎回、失業した方、年金暮らしの方、子育て世代、学生・留学生ら、100人を超える来場があります。来場者アンケートでも、「最近、お米も野菜も食べていない」「1日、2食ないし1食」「失業して無収入」「失業保険が切れ、短期バイトも断わられた。生保申請しても断わられる」「国保料が払えない」などの声が寄せられています。
負担軽減で支援してほしい要望のトップが、消費税減税(49%)。次に、国民健康保険料の引き下げ(29%)、医療費負担の軽減(24%)と続きました。
京都市では、40代夫妻と未成年2人の4人世帯(所得300万円)だと国保料は年間約52万円。25年度の算定では10%近い値上げが予定されています。高くて納付できず、「資格証明書(保険証の取り上げ)」が約2000件、「短期証」が5000件を超える実態(22年度)があり、今後、ますます保険証を持てない人が増えないか本当に心配です。
相談会でも滞納、納付の相談に応じていますが、この間取り組んでいる国保料引き下げ署名など、各自治体や国に対し、社会保障としての国保を守る運動が大事だと思います。
倉林議員は国会質問で、全日本民医連が毎年実施する「経済的事由による手遅れ死亡事例調査」の結果を紹介して、国保料値下げや窓口負担の軽減のため、公費負担の増額を政府に要求しています。看護師出身で、医療、福祉の専門家。国会に患者や医療現場の声を届ける、なくてはならない議席だと思います。
社会保障削減と正面対決できる
国保は、国民皆保険制度の土台。「いつでもどこでもだれもが、保険証1枚で必要な医療を受けられる」仕組みです。日本国憲法25条に基づき、社会保障制度を充実せよと迫る論戦に期待しています。
京都民医連中央病院に勤務していたころ、看護師だった倉林さんと労働組合で一緒だった時期があります。当時から気後れすることなく行政にも意見する姿勢が評判でした。8兆円もの軍事費には手をつけず、年間4兆円の社会保障費の削減を狙う政府とも正面から対決できる議員だと思います。