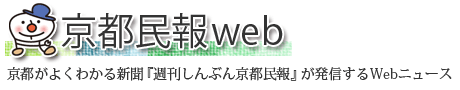困窮実態ぶつけ保護基準引き上げ迫る 〈宝の議席必ず 倉林明子参院議員の実績〉物価高騰が追い打ち「生存権脅かす事態に」

生活保護制度を巡って、政府による「生活扶助」基準額の引き下げは違憲・違法だと、制度利用者が全国で声を上げた「いのちのとりで裁判」で、「違法」と認める司法判断が続いています。京都訴訟の控訴審でも先月、大阪高裁で逆転勝訴。第2次安倍政権(12年発足)の下で強行された史上最大の大幅引き下げ(最大で10%減)に対し、たたかいが世論を変化させています。これらの運動と連動し、国会で政府を追及してきたのが倉林明子参院議員です。利用者の声を届け、生活保護基準の引き上げや運用改善を求めています。
保護費10%削減掲げて政権復帰
「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利どころか、生存権さえ脅かされている」。倉林議員は、物価高から暮らしを守れと、生活保護基準の引き上げを政府に迫りました(24年12月19日、厚生労働委員会)。
食費や光熱水費など日常生活費に当たる「生活扶助」基準額の引き下げ(平均6・5%、3年間で670億円)が強行されたのは13年。自民党が総選挙公約に生活保護給付10%削減を掲げて政権復帰した翌年でした。そこへ近年の異常な物価高騰が追い打ちをかけ、生活保護利用者の生活は過酷を極めています。
この質問で倉林議員は、全京都生活と健康を守る会連合会(京生連)が実施した利用者の生活実態アンケートを基に、「1日3食、食べることも毎日お風呂に入ることもかなわない」「香典が用意できず親戚の葬儀にも行けない」という実情を紹介。夏の猛暑にクーラーもないアパートで亡くなっていた事例まで発生したと告発し、「生存権さえ脅かされている現状から目を背けてはいけない。生活保護費の引き上げは待ったなしだ」と訴えました。
「現在の対応や社会情勢の動向も踏まえ検討」と反復する福岡資麿厚労相の答弁に対し、倉林議員は、直近3カ月の物価上昇率を上乗せして基準を変更する方法に改定(23年)したドイツの例を提示。生活保護基準となる最低生活費に合わせて課税最低限を引き上げ、低所得者全体の収入の底上げと購買力の向上にもつながっている、と物価高に見合う引き上げを重ねて求めました。
安倍政権が行った基準改定については、意図的に大きくした物価下落率を根拠に生活扶助費を減額した「物価偽装」だと批判し、社会保障審議会の部会にも諮らず強行したのは、自民党の選挙公約があるからではないかと指摘。引き下げの撤回、生活扶助基準の見直しを要求してきました。
申請阻む「扶養照会」なくせと
コロナ禍は、失業や収入減の影響で生活に困窮する人を増やしました。しかし、住まいを失い、手持ち金が数百円になっても生活保護の利用に進まない問題を取り上げました(21年3月30日、厚労委)。倉林議員は、申請をためらう要因に「扶養照会」(経済的援助ができないか申請者の親族に問い合わせる)があると指摘。制度上「扶養の可否は保護の要否判定に影響を及ぼすものではない」という扱いかと問うと、田村憲久大臣(当時)は、「(生活保護の要否判定の)要件ではないので、申請は受け付ける」と答弁しました。
これを受けて倉林議員は、現場では、要否決定前の扶養照会が実質的に要件と同様に扱われていると示し、「扶養照会があるから申請につながらない。申請時の扶養照会は取りやめる。最低でも申請者の同意を条件とすべき」と主張しました。困窮者支援団体の運動や働きかけと相まって、厚労省は同日、運用を一部改善する通知を発出。申請者が拒否し、理由を説明すれば照会しない対応に一歩前進しました。
「休学や退学も」大学生も対象に
また、現制度では、大学生が生活保護利用の対象外になっている問題を追及(22年6月7日、厚労委)。家計の急変やアルバイト収入がなくなるなどで困窮した場合、休学か退学を迫られることを指摘し、「生活保護法は国が生活に困窮するすべての国民に対し必要な保護を行う」とあり、大学生も対象にするよう要求。「当事者だけじゃなくて、社会にとっても学びが中断されることは損失になる」と説きました。

市民を代表する京都の貴重な議席
いのちのとりで裁判全国アクション共同代表、弁護士 尾藤廣喜さん
厚生省(当時)の職員時代に生活保護制度も担当し、弁護士になってからも長年、同制度の改善・充実を求める運動に携わっています。東京での全国規模の集会をはじめ、小規模の集まりでも倉林さんに会うことが多くありますが、いつも当事者を励ましてくれます。
倉林さんには、現場の実態や弱い立場の人の声から問題点を学ぼうとする姿勢があり、その視点で政策を考える優れた人だと思います。
昨年、生活扶助費を一昨年の状態に戻すのに単身で13%くらい引き上げる必要があると試算して国に要望書を提出しました。倉林さんは国会質問でそれも反映させて、物価高騰に見合った生活保護基準の引き上げを求め、また、生活扶助費の全額を支給しない違法行為が問題になっている群馬県桐生市の生活保護行政の是正も追及してくれました。まだまだ、取り上げてほしい課題があります。
生活保護基準は、利用者だけに関係するものではなく、就学援助、年金、施設入所の基準などにも影響する、ナショナルミニマム(国が憲法25条に基づき全国民に対し保障する 「健康で文化的な最低限度の生活」水準)なんです。
だから、第2次安倍政権は、生活保護基準を引き下げれば、連動して他の給付削減もできると考えたのでしょう。
この生活扶助費引き下げに対し、違法だと声をあげた「いのちのとりで裁判」(*)の京都訴訟の控訴審で、逆転勝訴(3月13日)、続く札幌高裁、東京高裁(2件)も勝訴しました。10年来の運動が世論を変え、高裁判決では6勝4敗です。5月27日には、最高裁の弁論期日も入りました。
司法には、原告らの引き下げ処分を取り消し、元に戻す拘束力がありますが、保護制度利用者全員の救済は政治の役割に期待するところです。
現政権は、防衛費をGDP比2%に倍増し、社会保障費を抑制する傾向にあります。これを転換し、社会保障費を増やす必要があります。防衛費を減らし、大金持ち優遇税制や特定の半導体企業への補助金を見直すなど、税金の使い方を正せば財源はあります。
この見解は倉林さんも同じ立場だと思います。看護師時代の原点を忘れず、何よりも命と暮らしを大切にし、弱い立場の人の声を熱心に取り上げているのが倉林さん。市民を代表する貴重な議席だと思います。

利用者の思いを国に届けてくれる議員
「京都 新・生存権裁判」原告 竹井登志郎さん
生活保護基準の引き下げは、憲法25条で保障される生存権の侵害にあたる、と自らの生活はもとより、様々な制度に影響する問題と考えて原告になりました。大阪高裁で逆転勝訴判決(3月13日)が出て、「声を上げて良かった」とみんなで喜び合いました。
病気がもとで生活保護制度を利用しはじめて2年ほどして、生活扶助費が減額されました。その後も家賃補助、冬季加算なども減らされて、生活費の削りようがない状態を続けています。食事の品数や入浴(シャワー)の回数も減らして節約。家電製品が壊れても購入は困難です。
京都地裁では原告の生活実態をまったく見てくれず、残念な思いをしただけに、高裁で窮状が届いたのはうれしいです。
政治の分野では、倉林明子さんが、裁判のことや制度利用者の声を取り上げ、生活保護基準の引き上げを求めてくれていることは、とても心強いです。
先日(3月24日)も参院厚労委で、全京都生活と健康を守る会連合会(京生連)の生活保護世帯実態アンケート(157人)を再度紹介し、大阪高裁判決にもふれて、国は生活保護利用者に謝罪せよ、上告するな、とただしてくれました。私たちの生活実態、思いを国に届けてくれる数少ない議員です。自身も苦労人で、京都市議時代から生活に困窮する多くの人の相談にのってきた経験があり、低所得者の味方だと思います。
石破首相がお土産だといって、新人議員に10万円の商品券を配った問題は、庶民感情を逆なでするもの。税金が原資との疑いもあります。税金を庶民の生活保障に使う政治に改めてほしい。そのためにも、新・生存権裁判勝利と倉林さんの3選を同時に勝ち取る決意をあらたにしています。