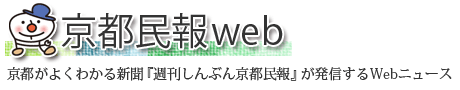ウナイ=女性たちの行動に希望が ドキュメンタリー『ウナイ 透明な闇 PFAS汚染に立ち向かう』平良いずみ監督インタビュー/8月22日から京都シネマで上映

発がん性とともに、低出生体重児のリスクが高まるなど深刻な健康被害を及ぼす恐れのある有機フッ素化合物(PFAS)の汚染実態の調査や、法規制を求めて立ち上がる国内外の女性たちを取材したドキュメンタリー『ウナイ 透明な闇 PFASに立ち向かう』が8月22日から、京都シネマ(京都市下京区)で上映されます。平良いずみ監督に、映画製作の動機、取材した女性たちの取り組み、日本のPFAS規制などについて聞きました。

─PFAS被害について取材しようと考えたきっかけは
2016年に沖縄県が北谷(ちゃたん)浄水場(北谷町)の水源から高濃度のPFASが検出されたと、発表しました。
粉ミルクを溶いた水が
北谷浄水場は、那覇市、沖縄市を含む、沖縄県民約45万人に水を供給している施設です。水源は米軍嘉手納(かでな)基地近くにあり、玉城デニー知事は記者会見で「米軍基地の影響である蓋然(がいぜん)性が高い」と述べました。
当時私は、その浄水場の水道水で粉ミルクを溶き、わが子に与えていました。その水が汚染されていると知り、不安と怒りで目の前が真っ白になりました。
しかし、こんなひどいことは政治が動いて解決してくれると静観していました。ところが、日米地位協定があるために米軍基地への立ち入り調査はできず、原因が特定されないままで、法的規制も進みませんでした。
そんなときに、地元のお母さんたちが「水の安全を求めるママの会」を立ち上げました。
沖縄テレビのディレクターをしていた私は、取材を始め、ドキュメンタリー番組「水どぅ宝」(2022年)、「続・水どぅ宝」(24年)を製作しました。この問題を映画にしようと昨年夏にテレビ局を退職し、改めて一から取材を重ねました。
─映画のタイトルを「ウナイ」としたのは
「ウナイ」は沖縄の言葉で「女性たち」という意味です。PFASの問題で表だって声を上げている人たちは、圧倒的に女性が多かったからです。
PFASの発生源は、軍や大企業と見られる場合が多く、米軍や問題企業は、毒性を知りながら、使用・製造してきたことがジャーナリストの取材などで明らかになっています。
国連の会議で訴えるまでに
女性たちは、軍事や経済的利益よりも命や人権が大事というシンプルなメッセージを発信し、強大な相手であっても挑んで世の中を動かそうとしています。そこに希望があると感じました。
作品では、そのような女性たちのたたかいを紹介しています。沖縄のお母さんたちは、本当に勉強して、地元の町や市、そして国と交渉してきました。地元の議員となって、調査や対策を求めています。お母さんが、奮起して国連人権理事会で訴える姿は実に感動的です。
アメリカのミネソタ州では、PFASを製造していた大手化学メーカーの工場があり、周囲の住民の多くががんで命を落としていました。20歳で末期がんとなったアマラ・ストランディさんは、これからの子どもたちに自分のような思いをさせたくないと、州議会で規制を訴え、世界で最も厳しい規制法実現に道を開きました。
イタリアのベネト州では、約35万人が飲んでいた水道水に高濃度のPFASが含まれていたことが発覚し、お母さん3人が呼びかけて市民団体を結成しました。数カ月後、数千人がパレードして社会問題化した結果、汚染源となった企業の刑事責任を認める有罪判決を勝ち取っていきます。
─世界的にPFASに対する規制は強まっていますが、日本の対策をどう思いますか
米国やEUでは、胎児への健康の悪影響が最新の研究で分かっており、国民の運動もあって規制値を厳格化したり、法的拘束力を持つものにしています。
PFASのうちPFOSとPFOAは、疎水性と疎油性に優れ、幅広い用途で使われてきました。
汚染の広がり人ごとでない
米国の規制値は、この2物質、それぞれで水道水1リットルあたり4ナノグラムとしています。それに対して、日本は、はるかに緩い1リットルあたり50ナノグラムを暫定目標値にしています。この値を来年の4月、基準値にしようとしています。
PFAS汚染を巡っては、水道などで高濃度の汚染が確認されている地域だけの局所的な問題と考えるかもしれませんが、実際には、影響は日本全体におよんでいます。PFASは分解されないため、魚介類の体内に蓄積されますし、家庭で使用するフライパンなどのコーティング剤としても使用されてきたからです。
この映画を見て、人ごとでないと知ってもらえればと思います。