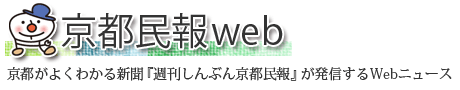最後の慰霊祭「不戦」固く誓う 舞鶴空襲学徒犠牲者慰霊祭/空襲被害発信に「大きな役割果たした」

終戦直前の1945年7月の米軍による舞鶴空襲から80年を迎えた7月29日、「舞鶴空襲学徒犠牲者慰霊祭」(慰霊碑管理委員会主催)が舞鶴市の共楽公園にある慰霊碑前で行われました。参列者は「人と人が殺し合うことは絶対にあってはいけない」と戦争を二度と繰り返さない決意を固め合いました。同慰霊祭は碑を建立した2014年から毎年続けられてきましたが、同管理委員会の高齢化のため、今回で最後の開催となりました。
舞鶴空襲があったのは45年7月29日午前8時35分頃で、米軍が長崎型原爆を模した大型爆弾を旧海軍工廠に投下。勤労動員されていた京都師範学校、洛北実務女子学校、第二商業学校の学徒19人、舞鶴高等女学校の教員1人ら、97人が犠牲となりました。翌30日にも米軍機による同工廠や軍港への攻撃が行われ、83人が亡くなりました。
慰霊碑建立は、舞鶴空襲で負傷し、両目を失明した故橋本時代さん(当時、洛北実務女子学校生徒)が、碑管理委員会の関本長三郎事務局長に、「犠牲になった友のため、形に残るものを」と語ったことがきっかけです。
14年には、市民らの寄付により旧工廠跡を見下ろす同公園に建立。犠牲となった学徒と教員の名前が刻まれています。
「学徒の思いを“矢弾”に」国策告発し、平和を希求
慰霊祭には、工廠に動員されていた学徒の遺族や地元住民らが参加。当時、火薬工廠に動員されていた小坂光孝・同管理委員会委員長(95)のメッセージを、日本共産党舞鶴市議の小西洋一氏が代読しました。
小坂氏は、碑建立のための市民らの協力に感謝の言葉を記した上で、「慰霊祭は敗戦直前の軍事生産を支えた学徒の思いを『矢弾にした』国策を告発し、平和を希求する市民と学徒の対話する所」であったと振り返りました。
京都師範学校を前身とする京都教育大学の太田耕人学長があいさつし、「忘れてはならない悲劇。京都教育大学は、この悲劇を大学の歴史の中に位置づけ、今後も語り継いでいく責任を感じている」と述べました。
京都師範学校の生徒で空襲を経験した故・内藤昇さんの長男・昌彦さんが遺族を代表してあいさつ。昇さんは21年の慰霊祭まで参加し、「みじめでむごたらしい戦争だけは繰り返してはならない」と訴えてきました。
昌彦さんは、「ドラム缶の棺(ひつぎ)に油をかけ荼毘(だび)に付した。死んでも無念の思いで口を開いていた友。戦争は人を異常にする」「戦争だけは…戦争だけはあかんのや。人と人が殺し合うことだけは絶対にあってはいけない」という父の言葉を紹介し、「実際に戦争を体験し、死と直面した毎日を送らざるを得なかった者の言葉です。父の遺言だと思います」と述べました。
関本事務局長は、「かん口令」が敷かれ、空襲の実態が戦後も部分的にしか伝えられてこなかったと指摘。碑建立と慰霊祭を通じ、「報道もされ、市民の中に多く語られるようになったことは、この碑が大きな役割を果たしたと思っています」と述べました。