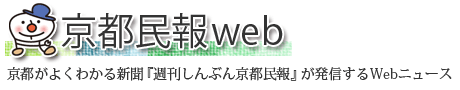食と農守る運動さらに 新婦人・農民連「産直運動」35周年交流会/「ミサイルより毎日のごはん」怒りのデモも

食の安全を考え、日本の農業と食料を守る農民連と新婦人の「産直運動」35周年を記念し、農民組合京都府連合会(上柿直一会長)と同産直センター、新日本婦人の会京都府本部(澤田季江会長)は5月11日、京都市南区の京都テルサで「食べることをまんなかに つながる産直交流会」を開きました。生産者23人、180人超が参加。記念講演に耳を傾け、マルシェや生産者との交流企画で親交を深めた後、「農政怒りのアピールデモ」と称してJR京都駅八条付近口まで行進しました。
開会あいさつで上柿会長は、〝令和の米騒動〟や食料品の高騰などで食料への関心が高まり、いま「産直運動」の意義が輝いていると強調。米の需給と価格の安定への責任を投げ捨てて、長年、農家に減反を押し付けてきた自民党農政を批判し、「農家と消費者が団結し、農業と胃袋を守る運動に引き続き取り組もう」と訴えました。
講演は、農民運動全国連合会(農民連)の藤原麻子事務局長が「日本が一番に飢える国? 産直運動ひろげて世直し」と題して行いました。藤原氏は、農民連と新婦人の「産直運動」が、政府が進める米国の食糧戦略に抗して、日本の農業と安全な食料を守る運動として1990年にスタートし、「国民合意」を大切に歩んできた歴史を振り返り、直近でも種苗法改悪に反対して一緒に声をあげた経験を紹介。「改悪されたが、都道府県単位で条例として制定される動きが広がっている」と激励しました。
日本の食と農の現状については、農業生産基盤の弱体化や担い手減少、栄養不足人口の増加などを指標で示し、「歴史的岐路にある」と指摘。この危機の打開策として、農民連が目指すアグロエコロジー(生態系を生かした持続可能な農業)の運動を紹介するとともに、「〝一口でも、一箸でも国産を食べよう〟を合言葉に、給食無償化や地場産食材の活用を広げ、自治体ごとの食料自給率向上を目指そう」と呼びかけました。
怒りのデモ行進では、「米不足、米価高騰は政府の責任 日本の食と農、暮らしを守れ」の横断幕を先頭に、「令和の百姓一揆」ののぼり、「戦争の準備より国民の食を守ろう」「ミサイルより毎日のごはん」などのプラスターで要求をアピール。「軍事費よりも農業予算」「選挙で変えよう」と声を響かせました。