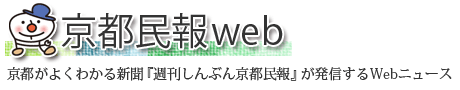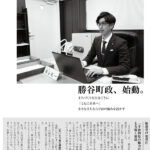『女工哀史』には“社会は変えられる”というメッセージが詰まっている 与謝野町で細井和喜蔵没後100年記念祭/文学碑建立、講演会・シンポジウムも

文芸評論家・斎藤美奈子さんが記念講演
紡績工場の過酷な労働を告発したルポルタージュ『女工哀史』の出版と著者の細井和喜蔵(1897~1925)の没後100年の記念祭(実行委員会主催)が11月22日、和喜蔵の故郷である与謝野町で行われました。文学碑の除幕式や文芸評論家の斎藤美奈子さんの記念講演が行われました。斎藤さんは『女工哀史』には、理不尽に対して声を上げ、社会は変えられるという現代にも通じるメッセージがつまっていると評しました。
和喜蔵は、12歳から地元の機屋で働き、13歳で大阪に渡り紡績工場で機械工になりました。22歳で東京に出た後、病気のため仕事をやめて文筆業に専念。労働組合の活動や労働運動に参加しました。1925年7月に代表作『女工哀史』を刊行し、翌月に28歳で亡くなりました。
文学碑(横幅1㍍30㌢、高さ90㌢)は、和喜蔵の子ども時代の遊び場だった鬼子母神境内に建立。碑文には自伝的所説「奴隷」の冒頭部分で、故郷の師走の風景を描写した「積雪は涯(はて)しなく続く水銀の海原に似て…」という文章を刻みました。
除幕式には約150人が参加。細井昭男実行委員長が「地元、特に子どもたちに和喜蔵のことを知ってほしい。これが始まりです」とあいさつ。斎藤さんは、「(和喜蔵は)労働者、特に女性の労働実態を告発し、戦前、戦後にどれだけの労働者が励まされたことだろうか」と語りました。
除幕式後に同境内に建立されている顕彰碑前で碑前祭を実施。「細井和喜蔵を顕彰する会」の松本満代表が、顕彰の取り組みについて、「働く者の未来に灯りをともす一助になることを念願する」という祭文を捧げました。

紡績工場の過酷実態告発「今で言えば公益通報」
記念講演で、『「女工哀史」は生きている』(岩波ブックレット、松本氏との共著)などの著作がある斎藤さんは、「女工哀史」は、過酷な労働実態を詳細に告発したものだと紹介。「全てを描いてやるんだという執念のたまもので、無名の若者の実名告発本だった。今でいう公益通報ともいえる」と語りました。
その上で、厳しい現実を描きながらも、「和喜蔵の作品は絶望していない。社会は変えられるし、変えていこうというメッセージが詰まっている」と強調。格差が拡大する現代において「『女工哀史』の世界はまだあると思う」と述べ、「あきらめない意志と、おかしいことはおかしいと言っていい、と学ぶ意義は大きい」と語りました。
記念講演後のシンポジウムでは、細井実行委員長、紙芝居動画「細井和喜蔵ものがたり」を制作した地元の読み聞かせグループ「マザーグースの会」の新田雪江さん、斎藤さん、和喜蔵の妻・高井としおの評伝小説「不屈のひと」著者の石田陽子さんが語り合いました。
石田さんは、としおは「女工哀史」の共作者ともいえる人物だとし、「どんなひどい絶望的な状況でもあきらめなかった。この人を忘れないでほしいとタイトルにその思いを込めた」と語りました。
同日には、和喜蔵の詩や短編小説などを収めた記念誌『「女工哀史」から百年』も出版されました。