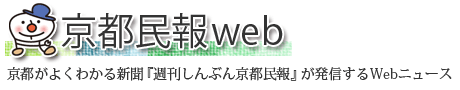【参院選2025】包括的性教育実施へ大いに期待/「包括的性教育推進法の制定をめざすネットワーク」事務局長、立教大学名誉教授・浅井春夫さん

ネットワークでは、性や人間関係、性の多様性などについて、人権と科学的根拠に基づき幅広く学ぶ「包括的性教育」が、乳幼児から発達に応じて学校や社会で推進されることを目指しています。しかし、学習指導要領では、妊娠の経過に関する内容を制限する「はどめ規定」があるため、包括的性教育の妨げとなっています。
政府が「はどめ規定」にこだわってきた背景には、女性や子どもの性を管理する家父長的な価値観が横たわっています。国連子どもの権利委員会などは日本政府に再三、包括的性教育の実施を勧告してきました。
ネットワークでは昨年、日本共産党の国会議員団と懇談し、そこで、ジェンダー平等委員会の責任者である倉林さんと出会いました。包括的性教育の実施は、性の健康と権利、子どもの教育を受ける権利に対応するもので人権の一つです。
倉林さんは、問題の本質を押さえ、年齢・発達段階に応じた「包括的性教育」の実施を政策に位置づけてくれました。党の議員の方々の国会質問にも結実しました。
ジェンダー平等の実現と不可分な包括的性教育実施へ、政治の責任は大きいと本腰をいれてくれる倉林さんに期待します。