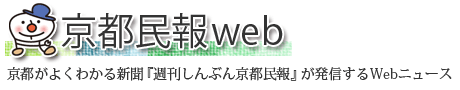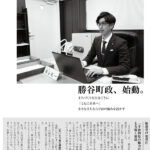国際平和都市のシンボルに 布袋山保存会が展示会 「屏風祭―渡来懸装(けそう)品の謎」

応仁の乱後の1500 (明応9)年に祇園祭の前祭(さきまつり)に巡行し、現在は休み山となっている布袋山の復活を目指す一般社団法人祇園祭布袋山保存会(川島義明会長)は6月16日から同19日まで、京都市中京区のNTT西日本三条コラボレーションプラザで展示「屏風祭―渡来懸装品の謎」を行いました。
同保存会は、布袋山について知ってもらおうと毎年、展示や講演会を行ってきました。祇園祭期間中に、商家の玄関先などに、屏風(びょうぶ)などを飾る「屏風祭」と呼ばれる風習があることから、今回は「屏風祭」と銘打ち開催。布袋山があった中京区姥柳町に、かつて南蛮寺があったことにちなみ、同寺や南蛮文化に焦点を当てた企画となりました。
南蛮寺は、イエズス会の京都での布教の拠点として、1576 (天正4)年に献堂式が行われたとされています。正式名「被昇天の聖母教会」と言い、高層で、「上から見られる」と住民から反発があったものの、織田信長の理解もあり完成にこぎつけました。設計、木材調達は、キリシタン大名として知られる高山右近が行いました。その姿は、安土桃山時代の絵師・狩野永徳の弟である狩野宗秀(そうしゅう)筆による「扇面洛中洛外図六十一面」の一つ「都の南蛮寺図」(神戸市立博物館蔵)にとどめており、瓦ぶき3階建てだったとみられます。87年、豊臣秀吉によるバテレン追放令後に破壊されました。
1973年に同志社大学考古学研究室が森浩一教授の指導により行った発掘調査で、同寺のものと思われる礎石や煙管(きせる)、硯(すずり)などが検出されました。
同展では、「都の南蛮寺図」や「南蛮屏風」(南蛮文化館蔵)の複写や、南蛮寺と金沢城天守閣の類似性を指摘した論考、布袋山の巡行した風景を想像して描かれた絵などが、展示されました。
川島会長は、「懸装品や衣装には、南蛮文化を取り入れたものを考えています。世界で戦争が起きるなか、中国由来の布袋さんの名を冠し、西洋由来の歴史や文化取り入れた布袋山を国際平和都市京都のシンボルとして盛り立て、復興させたい。市民のみなさんも力を貸してほしい」と語りました。