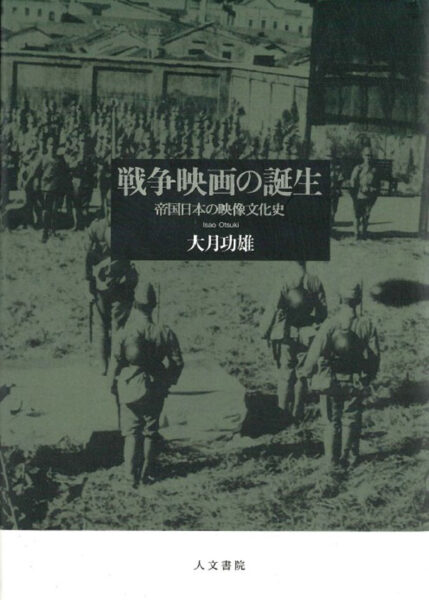戦争映画の中の批判的リアリズムを検証『戦争映画の誕生―帝国日本の映像文化史』/著者・大月功雄氏とインディペンデント・キュレーターの長谷川新氏が出版記念トーク

20世紀に日本でつくられた戦争映画と製作者・批評家を考察した労作『戦争映画の誕生―帝国日本の映像文化史』(人文書院)がこのほど出版されました。本書出版を記念し、筆者で立命館大学人文科学研究所客員研究員の大月功雄氏と、インディペンデント・キュレーターの長谷川新氏のトークイベントが11月15日、京都市左京区の大垣書店高野店で行われました。
大月氏は1987年生まれ。同学大学院博士課程を修了し、博士(社会学)。同学国際平和ミュージアムの学芸員も務めています。高校入学時、イラク戦争の報道に衝撃を覚えて戦争とメディアの関係に関心を持ちました。
2015年の安保法制の議論の中で、反対していた同世代の若者たちが祖父母の戦争体験を語るのを見聞きし、将来、証言者がいなくなった場合、戦争の記録としての戦争映画の役割の重要性が増すと考え、研究してきました。博士論文に加筆したものが、今回の『戦争映画の誕生』です。
トークイベントで大月氏は、日本の戦争映画の研究の歴史を振り返りました。1995年に出版された米国のピーター・ブラウン・ハーイの『帝国の銀幕―十五年戦争と日本映画』(名古屋大学出版会)は、日本において戦時中は(非文化的な)「暗い谷間」の時代だったとして、映画人らは大量転向をよぎなくされ、映画を国家のプロパガンダ映画へと変えたと描いていると解説。
しかし、その後、この主張に対しては、日本の研究者からも批判が相次ぎ、戦時期は、大正デモクラシーと戦後民主主義の間に挟まれ、戦時期の文化においても連続性があるとの提起がなされるなか、この提起に応え、8年かけて戦争映画の分野で研究し同書を書き上げたと述べました。
長谷川氏がとくに着目したのは、第2章「戦争映画のモダニズム」と第4章「戦争記録映画の時代」。第2章は、マルクス主義的映画批評家・岩崎昶(あきら)と1920年代の日本映画のモダニズムを牽引した映画監督・村田実を取り上げています。
第4章では、日中戦争期に東宝文化映画部で戦争記録映画を監督した亀井文夫を取り上げ、『上海』(38年)、『北京』(同年)、『戦ふ兵隊』(39年、上映禁止)の3部作を分析。戦争映画に国家のプロパガンダ的性格が強まるなか、亀井らがどのような表現の可能性を模索したかを検証しています。
第2章では、村田と岩崎はかつてプロレタリア映画の可能性をともに信じていたにも関わらず、村田がプロパガンダ的な戦争映画を撮るようになり、岩崎の批判に「君はユートピアを想像しているのか」と反論したことで2人の関係は決裂したものの、岩崎は最後まで村田に批評を通して連帯を呼びかけ続けたことを紹介。長谷川氏は、このドラマに心を動かされたと述べ、「切ない、いい話。エモ(感動)は強調されているけれど、当たれる限りの文献に当たりながら実証的に書かれている」と語りました。
大月氏は、岩崎は、プロキノ(日本プロレタリア映画同盟)の委員長まで務め、1930 年以後、撮影所外で自主映画を撮り始めたことが評価されているものの、それ以前に、言葉の力を信じ、無名の映画界の労働者たちも巻き込んだ批評運動を展開して、ファシズムに立ち向かう統一戦線をつくろうとしたことも本では盛り込んだと紹介しました。
第4章で、長谷川氏が注目したのが、38年に『北京』を巡り、亀井と映画批評家で行われた座談会。座談会中、監督である亀井が戦地に行っていなかったことが明らかになり、集中砲火を浴びた亀井が、周囲に押し切られ、次作から現地同行を約束した場面。
大月氏は、「亀井が(現地に)行ってみたら、想定していた戦争とは違う光景が広がっていて激しく動揺する。現実は美醜入り混じって存在しているのに、美だけ写していていいのか、国家は確かにそう言うかもしれないが、芸術の役割はそうではないのでは、と書いている。亀井の戦争体験は『戦ふ兵隊』という非常に不思議な作品が生まれた背景になっている」と解説しました。
最後に長谷川氏は、同書の終章「戦争映画のリアリズム」に、「深刻なのは、戦後日本社会が戦争映画の歴史的経験をおしなべて『暗い谷間』のなかに閉ざし込んでいったことで、その戦争映画のリアリズムのなかに賭けられていた批判的リアリズムの存在までも忘却していったことにある」と書かれてることに触れ、「映画のどの部分を信じているのか」と質問。
大月氏は、「現実を目の当たりにし、わがこととして考える力は映像に与えられてきたと思う。(ガザの現状を撮影したドキュメンタリーなど映画には)、新たな役割、人々の現実認識を変えるリアリズムの可能性が生まれている」と答えました。
なお、トークイベントには、第5章「戦争映画の技術」に登場する円谷英二が切り開いた特殊撮影の仕事に携わっていた人や日本画家らが参加し、2人の話に熱心に耳を傾けていました。